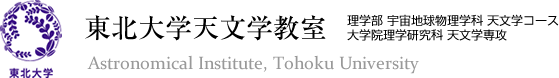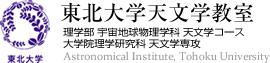談話会
Colloquium
談話会/Colloquium
[日時] 毎週月曜日15時から / [Date] Monday 15:00-
[場所] 青葉サイエンスホールまたは合同A棟203 / [Venue] Aoba Science Hall or 203 Science Complex A
会場確保の都合上時間が変更になる場合があります。
| No | Date and Time (YYYY/MM/DD, HH:MM-) |
Venue | Speaker | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1811 | 2025/04/14, 15:00- | Aoba Science Hall | 山田 智史(東北大学) | Accretion and Multi-scale Ejection Resolved by X-ray Observations from 1999 to 2025 |
| 1812 | 2025/04/21, 15:00- | Aoba Science Hall | Colton Hill(Chiba Univ.) | South Pole Science - Neutrino Oscillations and the IceCube Neutrino Detector Upgrade |
| 1813 | 2025/04/28, 15:00- | 203 Science Complex A | 堀米 俊一(東北大学) | Dwarf spheroidal galaxies as probes of dark matter |
| 1814 | 2025/05/12, 15:00- | Aoba Science Hall | Mochammad Wardana(東北大学) | Dwarf spheroidal galaxies as probes of dark matter, too: a stellar dynamics model refinement and test on the fuzzy dark matter paradigm |
| 1815 | 2025/05/19, 15:00- | 203 Science Complex A | Zhaoran Liu(東北大学) | Unveiling Hidden Star-formation within Galaxies at 0.9 < z < 1.7 |
| 1816 | 2025/05/26, 15:00- | Aoba Science Hall | 佐藤 優理(東北大学) | Multiwavelength afterglows from two-component jets in very-high-energy gamma-ray bursts |
| 1817 | 2025/06/02, 15:00- | 203 Science Complex A | 喜友名 正樹(東北大学) | The Role of Cold Accretion in the Formation of Supermassive Stars and Heavy Seed BHs |
| 1818 | 2025/06/09, 15:00- | 203 Science Complex A | Nuo Chen(東北大学) | Multiple Emission-Line properties of Hα emitters at Cosmic Noon probed by Broad-band excesses |
| 1819 | 2025/06/16, 15:00- | 203 Science Complex A | 野田 浩司(千葉大学) | Gamma-ray astronomy with CTAO LST and its status |
| 1820 | 2025/06/17, 15:00- | Science Complex C, Room N204 (Multipurpose room) | Chris Packham (Univeristy of Texas) | Future Flagships to Revolutionize Astronomy: Habitable Worlds Observatory & TMT/GMT |
| 1821 | 2025/06/18, 15:00- | 203 Science Complex A | Li Siyang (Johns Hopkins University) | Testing Hubble Tension Systematics with Cepheids, TRGB & JAGB |
| 1822 | 2025/06/23, 15:00- | 203 Science Complex A | 馬場 淳一 (鹿児島大学) | 天の川銀河の非軸対称構造と太陽系の軌道移動 Bar/Spiral Structures in the Milky Way and the Radial Migration of the Sun |
| 1823 | 2025/06/30, 15:00- | 203 Science Complex A | 横山 哲也 (東京科学大学) | Chemical and isotopic analyses of samples returned by the Hayabusa2 mission from the asteroid Ryugu |
| 1824 | 2025/07/07, 15:00- | 203 Science Complex A | 津久井崇史 (東北大学) | Understanding Thin and Thick Disk Formation by JWST and ALMA |
| 1825 | 2025/7/14, 15:00- | 203 Science Complex A | 志達 めぐみ (愛媛大学) | High Resolution X-ray Spectroscopy and Multi-Wavelength Monitoring of Accretion and Outflows in X-ray Binaries |
| 1826 | 2025/7/28, 15:00- | 203 Science Complex A | 稲吉 恒平 (北京大学) | The emergence of the first massive black holes |
| 1827 | 2025/9/5, 15:00- | 203 Science Complex A | Max Meier (Chiba Univ.) | Neutrinos at the Highest Energies: IceCube’s Window into Ultra-High- Energy Cosmic Rays |
| 1828 | 2025/9/18, 15:30- | Aoba Science hall | 河原 創 (ISAS/JAXA) | 天文学の理論と観測を繋ぐ微分可能プログラミング |
| 1829 | 2025/10/6, 15:00- | 203 Science Complex A | 松井 理輝 (東北大学) | Prediction of multi-messenger emissions associated with X-ray flare of GRBs |
| 1830 | 2025/10/9, 10:00- | 203 Science Complex A | Lucy Olivia MCNEILL (Kyoto Univ.) | Binary stellar evolution of double white dwarf binaries: theoretical challenges revealed by ZTF |
| 1831 | 2025/10/13, 15:00- | 203 Science Complex A | 星 篤志 (東北大学) / 天崎 賢至 (東北大学) | Exploring the Relationship Between Low-Mass Supermassive Black Holes and Their Host Galaxies at Intermediate Redshift / Cosmic very small dust grains as a natural laboratory of mesoscopic physics |
| 1832 | 2025/10/20, 15:00- | 203 Science Complex A | 千葉 凛平 (東京大学) | Probing dark matter with resonant dynamics of the Galactic bar |
| 1833 | 2025/10/21, 10:00- | 203 Science Complex A | Gerhard Hensler (University of Vienna) | Extragalactic star formation in ram-pressure stripped gas clouds |
| 1834 | 2025/10/27, 15:00- | 203 Science Complex A | 山本 直明 (東北大学) / 金 滉基 (東北大学) | Young galaxy clusters/groups identified as overdensities of [OII] emission-line galaxies / 2次元一般相対論的Particle-in-Cellシミュレーションによる磁気圏由来フレア発生過程の解析 |
| 1835 | 2025/11/10, 15:00- | 203 Science Complex A | 鈴木 善久 (東北大学) / 及川凛 (東北大学) | Unveiling the formation of the Milky Way halo using Subaru Hyper-Suprime Cam / Mass loading into black hole jets in Active Galactic Nuclei |
| 1836 | 2025/11/11, 15:00- | 203 Science Complex A | Sebastiano Cantalupo (Univ. of Milan) | Illuminating the most massive Cosmic Web nodes and their relation with galaxies at z~3 with the help of quasars |
| 1837 | 2025/11/17, 15:00- | 203 Science Complex A | 熊田遼太 (東北大学) / 鈴木慧次 (東北大学) / 和田航汰 (東北大学) | 1型 X 線バーストの質量放出と電波対応天体 / 巨大惑星と原始太陽系円盤の1次元共進化計算による惑星形成環境の解明 / ストリーミング不安定性でつくられるダスト塊のスケーリング則と微惑星形成条件 |
| 1838 | 2025/11/26, 15:00- | 203 Science Complex A | 田邊ひより (東北大学) / 千葉公哉 (東北大学) / Salma Rahmouni (東北大学) | すばる望遠鏡レーザートモグラフィー補償光学のトモグラフィー波面推定の最適化 / Non-LTE Ionization Modeling in Neutron Star Merger Ejecta / Heavy Element Features in Early- and Late-Phase Spectra of Kilonovae |
| 1839 | 2025/12/1, 15:00- | 203 Science Complex A | 鍋田春樹 (東北大学) / 越水拓海 (東北大学) / 米永直生 (東北大学) | 非理想磁気流体効果を考慮した磁気乱流環境下でのダスト濃集 / 磁束輸送を考慮した孤立ブラックホール降着流の多波長放射モデル / 偏光輸送計算で迫るガンマ線バーストの放射メカニズム |
| 1840 | 2025/12/8, 15:00- | 203 Science Complex A | 高橋光明 (東北大学) / 舩木美空 (東北大学) / 浜田草太郎 (東北大学) | Development of ISP for Adaptive Optics using FPGA / Probing cold gas associated to protocluster and surrounding structures / 連星白色矮星合体残骸候補J005311の細長いフィラメント構造について |
| 1841 | 2025/12/15, 15:00- | 203 Science Complex A | Misato Fukagawa (Tohoku Univ.) | Unveiling the Structures of Protoplanetary Disks with High-Resolution Observations |
| 1842 | 2025/12/22, 15:00- | 203 Science Complex A | Jun Toshikawa (Tohoku Univ.) | The formation of galaxy clusters probed by the Subaru/HSC imaging and Ly-alpha spectroscopy |
| 1843 | 2026/1/7, 15:00- | Aoba Science Hall | Kohta Murase (Pennsylvania State Univ.) | Multimessenger Perspectives on High-Energy Cosmic Neutrinos |
| 1844 | 2026/1/19, 15:00- | 203 Science Complex A | Gavin Lamb (Liverpool John Moores Univ.) | Dust off the BOAT |
| 1845 | 2026/1/26, 15:00- | 203 Science Complex A | Fumihiro Naokawa (Univ. of Tokyo) | Cosmic birefringence |
| 1846 | 2026/2/17, 15:30- | 203 Science Complex A | 高橋慶太郎 (熊本大学) | SETIを次の段階へ |
| 1847 | 2026/2/27, 13:00- | 203 Science Complex A | Yuki Isobe (Univ. of Cambridge) | Tracing Early Chemical Enrichment in the Era of Ever-Growing JWST Data |
| 1848 | 2026/3/9, 15:00- | 203 Science Complex A | Jonathan Granot (Open Univ.) | TBA |
Title & Abstract
1811
2025/04/14 (Mon)
山田 智史(東北大学)
Accretion and Multi-scale Ejection Resolved by X-ray Observations from 1999 to 2025
To make a database of multiphase (e.g., ionized/dusty/neutral/molecular) outflows, we have launched a new project, X-ray Winds In Nearby-to-distant Galaxies (X-WING). As the first study of the X-WING project, we constructed a sample of 132 AGNs in z ~ 0-4 exhibiting blueshifted absorption lines of X-ray winds reported by the end of 2023. With a thorough investigation of the previous works, we created the database of outflow properties of 583 X-ray winds, including outflow velocities (Vout), outflow radii (Rout), and mass/kinetic outflow rates (Mout/Eout). The ultrafast outflows (UFOs) and slower warm absorbers cover the Vout range of ~100 to 100,000 km/s. Interestingly, we found a clear velocity gap around Vout ~ 10,000 km/s. Although the gap can be an artifact due to the confusion of the emission/absorption lines and Fe K edge in the 6-7 keV band, there is another possibility that the UFOs and galactic-scale outflows are physically disconnected. Moreover, we introduce our unprecedented high-energy-resolution spectra with XRISM operated from 2023 and provide new insights into the origin of the Vout gap and the plausible multi-scale structure of X-ray winds (e.g., Yamada+24b, ApJS; XRISM Collaboration+). Finally, we will also report the latest results of the UV-to-radio SED fittings and studies on multiphase outflows for the X-WING AGNs and discuss the accretion and multi-scale ejection in AGNs.
1812
2025/04/21 (Mon)
Colton Hill(Chiba Univ.)
South Pole Science - Neutrino Oscillations and the IceCube Neutrino Detector Upgrade
Of all the Standard Model particles, neutrinos are the least well understood. While significant global progress has been made in characterising neutrino oscillations, several key questions remain unanswered: what are the masses of the neutrinos, and do neutrino oscillations truly follow the standard three-flavour model? The cubic-kilometre IceCube Neutrino Detector located at the geographic South Pole is capable of precision measurements of neutrino oscillation properties by observing neutrinos produced from particle interactions in the atmosphere across a broad range of energies (GeV-scale) and path lengths, often travelling through the Earth. To increase IceCube's sensitivity in the GeV-range, the IceCube Upgrade will involve deploying a dense array of high-sensitivity optical modules up to 3 km deep into the Antarctic glacier at the end of this year. One of these flagship modules, the "D-Egg", was developed and tested in Japan as part of an international effort for the Upgrade, and features a factor 2.8 per-device improvement in sensitivity over the current generation detectors. With enhanced direction reconstruction and a lower energy threshold, the Upgrade is expected to probe the neutrino mass ordering at the 3 sigma level within 5 years, and observe tau-neutrino appearance after just one year of data taking. As of January 2025, all 292 D-Eggs have arrived at the South Pole, with approx. 30% having already completed pre-deployment testing. This seminar with focus on the progress of the IceCube Upgrade, including the South Pole activities of the 2024/2025 Antarctic On-Ice Season, and share the latest sensitivities for the IceCube Upgrade ahead of data-taking later next year.
1813
2025/04/28 (Mon)
堀米 俊一(東北大学)
Dwarf spheroidal galaxies as probes of dark matter
The presence of dark matter in our universe is one of the biggest open questions in particle physics, astronomy, and cosmology. Among several detection methods, astronomical observations can explore interesting parameter regions that are not easily accessible by collider or direct detection experiments. In this talk, we focus on one of the most promising targets: dwarf spheroidal galaxies (dSphs), which are dark-matter dominated satellite galaxies of the Milky Way.
We show recent results of dynamical analyses using the spherical Jeans equation, a standard tool in stellar dynamics, to constrain the dark matter density profiles of dSphs. To interpret these results in a cosmological context, we use a semi-analytical cosmological model called SASHIMI (Semi-Analytical SubHalo Inference ModelIng), which predicts subhalo properties such as mass and density structure. These predictions are used as priors in a Bayesian analysis to connect observations with theoretical dark matter models. For cold dark matter (CDM), we apply this framework to estimate the J-factors of dSphs, which are important for indirect detection studies. For self-interacting dark matter (SIDM), we extend the model to SASHIMI-SIDM, which includes the effects of self-scattering on subhalo evolution. By comparing with observed satellite galaxies, we derive quantitative constraints on the self-interaction cross section, showing how small-scale structures in dSphs can inform the fundamental properties of dark matter.
1814
2025/05/12 (Mon)
Mochammad Wardana(東北大学)
Dwarf spheroidal galaxies as probes of dark matter, too: a stellar dynamics model refinement and test on the fuzzy dark matter paradigm
The preference for cored dark matter density profiles in dwarf disk galaxies has long stirred
tensions over the internal structure of dark matter halos, further complicating the Cold Dark
Matter (CDM) crisis at sub-galactic scales. Kinematic measurements of stars in the even more
dark matter–dominated dwarf spheroidal (dSph) satellites of the Milky Way offer a promising,
less baryon-contaminated avenue to revisit these issues. As data on individual member stars
improve in both precision and sample size, dynamical estimates of their underlying mass
distributions are becoming increasingly accessible. However, the inferred dark matter density
profiles show significant variation. Some galaxies are more consistent with cored profiles, others
with cuspy ones, and some analyses report that both core and cusp profiles are equally plausible.
This may be a clue that the classic core–cusp problem is just the tip of a larger “diversity”
problem, and it certainly signals the need for more refined modeling to distinguish cores and
cusps apart more reliably.
We, therefore, attempt to extract more information contained in the non-uniform shape of the
line-of-sight velocity distribution, which is assumed to be fixed in traditional Jeans modeling. This
is achieved by invoking the stars’ higher-order velocity moments alongside their standard velocity
dispersion. We demonstrate the model’s improved capacity for recovering dark matter density
profiles and discuss its inherent limitations. In addition, we explore the implications of our model
within the context of fuzzy dark matter (FDM) theory, an alternative to CDM that gained
growing attention for its potential to reconcile observations and theory. We provide preliminary
constraints on the FDM particle mass necessary to address the core–cusp tension observed in
classical Milky Way dSphs.
1815
2025/05/19 (Mon)
Zhaoran Liu(東北大学)
Unveiling Hidden Star-formation within Galaxies at 0.9 < z < 1.7
Galaxies experience their most intense stellar growth at redshifts z = 1–3, yet a significant fraction of this activity is obscured by dust. In this talk, I will present a multi-wavelength, multi-tracer investigation that combines observations from JWST, ALMA, and Subaru to trace both the fuel for star formation and its by-products, interstellar dust, in galaxies at 0.9 < z < 1.7, immediately after the cosmic noon. Some of the key questions I aim to answer include: Where in galaxies and how much is dust involved in the starburst and secular phases? How is it related to the propagation of star formation and quenching within galaxies? And how do local and large-scale environments modulate the relation between star formation and dust properties?
To address these questions, I will present our work using a combination of tracers: the 3.3 μm PAH emission observed with JWST/MIRI to map dusty star-forming regions; Paα emission obtained through JWST/NIRCam WFSS to trace total star formation including hidden dusty component at high spatial resolution; CO(2–1) measurements from ALMA to probe the molecular gas reservoir fueling star formation; and Hα/Hβ-based dust extinction mapping across a z = 0.9 supercluster using Subaru narrow-band imaging. Together, these observations provide a comprehensive view of the gas, star formation, and dust cycle and reveal how internal processes and external environments shape galaxy growth during and shortly after the peak epoch
1816
2024/05/26 (Mon)
佐藤 優理(東北大学)
Multiwavelength afterglows from two-component jets in very-high-energy gamma-ray bursts
Gamma-ray bursts (GRBs) are the most luminous and violent explosive electromagnetic events in the universe. GRBs also have broadband afterglows, from radio to very-high-energy (VHE) gamma rays, which provide us with extensive physical information about their nature. Currently, it is widely believed that prompt gamma-ray photons are emitted by a relativistic jet toward us, and that the interaction of this jet with the surrounding medium of the source generates the afterglow. However, many fundamental questions remain unanswered: how is the relativistic jet formed, what is the origin of the central engine, and how is the multiwavelength afterglow radiated? In this talk, we explore the phenomena associated with the relativistic two-component jet, which consists of two top-hat jets with angularly equi-distributed energy with different opening angles, to investigate the formation mechanism of relativistic jets. In general, the GRB jets have an angular structure, which is also shown in previous hydrodynamic simulations. Such a structured jet is most simply approximated by a two-component jet. The two-component jet model has been motivated to explain the multiwavelength afterglow emission in some GRB events. Our two-component jet model successfully explains the multiwavelength afterglows of GRBs associated with VHE gamma-ray emission. These findings suggest that a structured jet, such as the two-component jet, is essential for explaining complex multiwavelength afterglows.
1817
2025/06/02 (Mon)
喜友名 正樹(東北大学)
The Role of Cold Accretion in the Formation of Supermassive Stars and Heavy Seed BHs
Supermassive black holes (SMBHs), with masses of 10^(6-10) Msun, are located at the center of most galaxies. Since their discovery, the origin of SMBHs has been a significant unresolved problem. Recent discoveries of distant quasars at the redshift z~10 highlight the challenge of their rapid formation. One promising candidate for SMBH progenitors is supermassive stars with masses of approximately 10^5 Msun. After forming, supermassive stars collapse directly into BHs of approximately 10^5 Msun, which can grow into SMBHs within enough time. A key challenge lies in understanding how to form them. Cold accretion has been suggested to play a crucial role in supermassive star formation, but it has not been studied intensively due to poor understanding of cold accretion in high-z low-mass halos. We perform cosmological simulations to investigate supermassive star formation driven by cold accretion. We first clarify that cold accretion emerges in high-z halos with masses of approximately 10^7 Msun. We then follow the subsequent star formation and discover that cold accretion forms dense, compact disc at the halo center, forming multiple supermassive stars. This indicates the ubiquitous formation of heavy seed BHs, ultimately growing into SMBHs.
1818
2025/06/09 (Mon)
Nuo Chen(東北大学)
Multiple Emission-Line properties of Hα emitters at Cosmic Noon probed by Broad-band excesses
The rest-frame optical spectrum of high-redshift star-forming galaxies is characterized by a number of crucial emission lines originating from the interstellar medium (ISM) within them, including the hydrogen recombination line and metal lines. These spectral lines serve as powerful indicators of the physical and chemical conditions in galaxies. In contrast to the traditional spectroscopic method, we introduce a new selection method to search for emission line galaxies based on their flux excess in broad-band photometry. More than 1,000 Hα emitters (HAEs) at 2.05 < z < 2.5 have been found in the ZFOURGE survey by our method, along with [OIII] and [OII] emission lines. Our measurements demonstrate good consistency with those obtained from spectroscopic surveys. We investigate the correlations between the equivalent widths (EWs) of these emission lines and various galaxy and ISM properties, providing insights into the nature of intense emitters. To investigate and resolve the rest-frame optical structures of these HAEs in remarkable detail, we further utilize the JWST-JADES data, which is an extremely deep survey overlapping with the ZFOURGE-CDFS field. The data enable us to perform a rest-frame optical, spatially resolved analysis on a subsample of the HAEs. We newly discover a population of kiloparsec-scale compact emission line regions (“Green Seeds”) with high EW[OIII]. Embedded within the host galaxy, many Green Seeds correspond to UV star-forming clumps and HII regions, indicating elevated starburst activity in them. Based on theoretical frameworks, we also discuss the formation and fate of Green Seeds. The systematic study of emission line galaxies conducted in this work has the potential to significantly deepen our understanding of galaxy structure and evolution at Cosmic Noon.
1819
2025/06/16 (Mon)
野田 浩司 (千葉大学)
Gamma-ray astronomy with CTAO LST and its status
Astronomy has developed by expanding the wavelengths of the electromagnetic waves. However, the sky observed with very-high-energy (VHE; >100 GeV) gamma rays is not yet understood well. Gamma-ray detection in TeV energies is the realm of the instruments called Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (IACTs). Currently a few IACT experiments are under operation, which led to discoveries of above 200 astronomical sources. However, they are not sufficient to fully understand the nature of the particle acceleration sites responsible for the gamma-ray emission. In particular, it is difficult to investigate transient objects, due to the complexity in the observations. Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) is the next-generation project in this field, and Large-Sized Telescope (LST) is one of its key instruments most sensitive in the energy range from 20 GeV to tens of TeV. In this seminar introduced are the physics motivations and prospects using the coming LSTs, as well as the status of the projects such as the construction and commissioning of the telescopes being built in La Palma, Canaries, Spain.
1820
2025/06/17 (Tue)
Chris Packham (University of Texas)
Future Flagships to Revolutionize Astronomy: Habitable Worlds Observatory & TMT/GMT
The coming decades will afford the chance to transform our knowledge of the universe and perhaps will reveal compelling evidence of life outside of the Earth. In this presentation I explore the facilities that will enable such advances, advancing the successes of the JWST and 8m ground based telescopes. Uniquely achieved through multi-national collaborations, leveraging the technical and scientific skills of those partners, as well as spreading the costs and risks, a revolutionary scientific future beckons.
Biography: See the WWW link here: https://chrispackham495e.myportfolio.com/about
1821
2025/06/18 (Wed)
Li Siyang (Johns Hopkins University)
Testing Hubble Tension Systematics with Cepheids, TRGB & JAGB
The Hubble Tension refers to a >5 σ discrepancy between local and cosmological
measurements of the Hubble constant (H0) and suggests the possibility
of undiscovered early-universe physics or underestimated systematics. Probing
the Hubble Tension necessitates intense scrutiny of the Cepheid-based
distance scale, which currently provides the strongest constraints on local
measurements of H0. One powerful approach to crosscheck systematics in
the Hubble Space Telescope (HST) Cepheid section of the distance ladder is to
develop and improve independent routes to measure distances to the same set
of galaxies and H0, such as those using the tip of the red giant branch (TRGB)
and J-region asymptotic giant branch (JAGB), or by adding an independent
anchor. I will present a sub-2% Cepheid distance to M31, which prepares
an additional anchor galaxy that can be used to construct the distance ladder
once a high-precision geometric detached eclipsing binary observation
is feasible, as well as work improving standardization and calibration of the
TRGB, including a 2D maximum likelihood formalism enabling Milky Way
field star calibrations and contrast ratio standardization in the maser host
NGC 4258. I will also present recent James Webb Space Telescope (JWST) TRGB
distances to 8 hosts of 10 Type Ia supernovae (SNe Ia), later expanded to 25 hosts,
which provides no evidence of a HST Cepheid systematic resolving the Hubble Tension,
in addition to a H0 measurement using JWST observations of the JAGB with an expansion
to 15 galaxies hosting 18 SNe Ia. While the JAGB remains promising as a tool that can
crosscheck Cepheid systematics, non-uniform asymmetry in its luminosity function,
caused in part by stellar contamination, presently limits the precision of this candle.
1822
2025/06/23 (Mon)
馬場 淳一 (鹿児島大学)
天の川銀河の非軸対称構造と太陽系の軌道移動
Bar/Spiral Structures in the Milky Way and the Radial Migration of the Sun
私たちが住む銀河「天の川銀河」は、宇宙に広く存在する「棒渦巻銀河」の一種 である。しかし、この事実が確立するまでには時間がかかった。これは、天の川 銀河が他の系外銀河では到達不可能な高い分解能で詳細に調べることが可能であ る一方で、我々がその内部に位置し、天の川銀河の全体像を見渡すことが容易で はないためである。しかし、位置天文観測衛星「Gaia」の革新的なデータによ り、天の川銀河の恒星系成分の理解が飛躍的に進展した。また、大規模シミュ レーションも発展し、最新の観測データの解釈に大きく貢献している。本講演で は、講演者らによるGaiaデータと大規模数値シミュレーションデータを用いた研 究に基づき、天の川銀河の基幹構造である渦状腕構造や棒状構造などに関する理 解の現状を紹介する。また、天の川銀河化学動力学進化の観点から太陽系の誕生 半径の推定、太陽系軌道移動に関する講演者による最近の研究成果を紹介する。
The Milky Way Galaxy, our home galaxy, is classified as a barred spiral galaxy—a type commonly found throughout the Universe. However, this classification was not established until relatively recently. One major reason is that, while the Milky Way can be studied with far higher spatial resolution than any external galaxy, we reside within it and thus lack a global, outside view. This limitation has long hindered our ability to understand its overall structure. Thanks to the revolutionary astrometric data provided by the Gaia satellite, our knowledge of the stellar components of the Milky Way has advanced significantly. At the same time, large-scale numerical simulations have also progressed and now play a crucial role in interpreting recent observations. In this talk, I will present our current understanding of the Milky Way’s fundamental structures—such as its spiral arms and central bar—based on studies using Gaia data and state-of-the-art simulations. I will also introduce recent research by our group on the birth radius of the solar system and its subsequent radial migration, discussed in the context of the chemo-dynamical evolution of the Milky Way.
1823
2025/06/30 (Mon)
横山 哲也 (東京科学大学)
Chemical and isotopic analyses of samples returned by the Hayabusa2 mission from the asteroid Ryugu
The recent success of asteroid sample return missions has led to significant advances in Solar System science. JAXA's Hayabusa2 successfully retrieved and returned to Earth a total of 5.4 grams of samples from the C-type asteroid Ryugu. Sample return missions are critical to the scientific community, particularly in the fields of planetary science and cosmochemistry. These missions provide pristine, terrestrially unaltered extraterrestrial materials, allowing detailed laboratory analyses that are not possible with remote sensing. The only other access to extraterrestrial materials is meteorites, but meteorites may have been contaminated by terrestrial materials during impact, during residence time prior to collection (meteorite finds), and during storage in meteorite collections prior to changes in curation protocols. Thus, the analytical data obtained in laboratories for samples collected by these missions will facilitate the understanding of the formation and evolution of the Solar System without bias from potentially contaminated data.
For the Hayabusa2 mission, six initial analysis teams (Chemistry, Rock, Sand, Gas, SOM, and IOM) and two Phase 2 curation analysis teams were established, each consisting of up to several dozen individual researchers. I was appointed deputy leader of the Chemistry team and was heavily involved in analyzing the chemical and isotopic compositions of the Ryugu materials. A series of analyses of these samples indicated that the mineral, chemical, and isotopic compositions of Ryugu bear a strong resemblance to those of the Ivuna-type (CI) carbonaceous chondrites. CI chondrites have been recognized as a unique group of meteorites with a chemical composition similar to that of the solar photosphere except for highly volatile elements (noble gases, H, C, N, and O) and Li, which was destroyed in the Sun by nuclear reactions. In the seminar, I will present the meaning and significance of the compositional similarity between Ryugu and CI chondrites. I will also present our recent activities in a new project called the Ryugu Reference Project (RRP), which was initiated to maximize the potential value of the returned sample, aiming to establish an international standard for elemental and isotopic abundances in the solar system using the Ryugu samples and other related extraterrestrial materials.
1824
2025/07/07 (Mon)
津久井 崇史 (東北大学)
Understanding Thin and Thick Disk Formation by JWST and ALMA
Present-day disk galaxies, including the Milky Way, exhibit two distinct structures: an older thick disk and a younger thin disk. However, the timing and mechanisms of their formation remain open questions, primarily due to observational limitations ― these structures had not been identified beyond z=0 until recently. Leveraging JWST’s superb capabilities, we have, for the first time, identified and investigated thin and thick disks across cosmic time, up to 10 Gyr ago. Our study reveals a consistent trend: in the earlier universe, more galaxies appear to have had only a single thick disk, while in later epochs, more galaxies showed a two-layered structure with an additional thin disk component. This suggests a sequential formation, in which galaxies first formed a thick disk, followed by the development of a thin disk embedded within it. Notably, thin disks formed earlier in more massive galaxies (disk downsizing). By linking disk structural properties with gas kinematics, we propose that the Toomre Q regulated disk formation naturally explains disk downsizing and disk geometric properties. Complementing this, ALMA observations probing the thick disk formation epoch z~4-5 allow us to investigate how thick disks may have formed in gas-rich systems. I will present how such formation likely proceeded through dynamical processes, such as stellar scattering driven by disk substructures common in gas-rich disks, as supported by observations and numerical simulations.
1825
2025/07/07 (Mon)
志達 めぐみ (愛媛大学)
High Resolution X-ray Spectroscopy and Multi-Wavelength Monitoring of Accretion and Outflows in X-ray Binaries
Accreting compact objects often launch powerful outflows: uncollimated disk winds and highly collimated relativistic jets. Studying these outflows is essential to understand the physics of accretion and the feedback processes to their environment. Galactic X-ray binaries are ideal targets for such studies. Thanks to their proximity and brightness, especially during active phases in the X-ray band, they provide valuable opportunities for sensitive observations close to the compact object. In addition, their strong variability and short characteristic timescales enable us to trace the evolution of the outflows across a wide range of mass accretion rates. Disk winds in X-ray binaries are often observed as blueshifted, highly ionized absorption lines in X-ray spectra. Resolve, the cutting-edge X-ray spectrometer aboard XRISM, is dramatically advancing our understanding of these winds through its unprecedented energy resolution. Moreover, the combination of XRISM’s high-resolution spectroscopy with multi-wavelength monitoring, allows us to study disk winds, accretion flows, and jets simultaneously, and to explore how these components may be connected. In this talk, I will present results from the latest XRISM and findings from our multi-wavelength observations of X-ray binaries, and discuss future directions and prospects for deepening our understanding of accretion flows and outflows.
1826
2025/07/28 (Mon)
稲吉 恒平 (北京大学)
The emergence of the first massive black holes
The JWST has detected massive black holes (BHs) with masses of 10^6-8 Msun within the first billion years of the universe. One of the remarkable findings is the discovery of "Little Red Dots" (LRDs), a unique class of AGNs with distinct spectral features. These newly identified populations provide key insights into early BH assembly, distinguished by several characteristics: (1) their high cosmic abundance, (2) BH-to-galaxy mass ratios exceeding the local value, (3) strong Balmer absorption features on top of broad emission lines, and (4) a cosmic occurrence rate with a characteristic rise and decline. In this talk, I will review these JWST discoveries, discuss possible theoretical interpretations, and explore their implications for BH evolution.
1827
2025/9/5 (Fri)
Max Meier (Chiba Univ.)
Neutrinos at the Highest Energies: IceCube’s Window into Ultra-High- Energy Cosmic Rays
Ultra-high-energy cosmic rays (UHECRs) produce astrophysical neutrinos (TeV+) inside their sources and so-called cosmogenic neutrinos (PeV+) on their journey through the universe. These neutrinos are unique messengers from the distant and violent universe, able to probe the sources of UHECRs. The IceCube Neutrino Observatory is the largest neutrino detector in the world, instrumenting a cubic kilometer of Antarctic ice to catch these rare and elusive particles.
In this talk, after briefly reviewing IceCube’s recent studies of astrophysical neutrinos, I will present IceCube’s world leading limit on the neutrino flux at the highest energies. For the first time the non- observation of cosmogenic neutrinos puts serious constraints on the composition of UHECRs. Finally, I put IceCube's limit into context of the recent observation of an extremely-high-energy neutrino in KM3NeT.
1828
2025/9/5 (Fri)
河原 創 (ISAS/JAXA)
天文学の理論と観測を繋ぐ微分可能プログラミング
機械学習技術の急速な進展は、新たなプログラミングパラダイム――自動微分に基づく微分可能プログラミング(Differentiable Programming, DP)をもたらしている。天文学は長らく、数値微分あるいはSymbolicな微分(つまりmathematicaとかsympy)を通じてデータ解析やシミュレーションにおける勾配情報を活用してきたが、DPによってコード内に導関数をこれまで以上に柔軟かつ効率的、正確に組み込むことが可能になった。
天体物理現象や宇宙論のモデルをDPの枠組みで定式化することにより、勾配ベースの最適化を行えるだけでなく、HMC-NUTS、Langevin Monte Carlo、変分推論といった勾配ベースのサンプラーを用いて大規模なパラメータ空間に対する堅牢なベイズ推論を実行することもできる。シミュレーションのレベルにおいても、DPはシミュレーターを推論パイプラインに直接組み込むことを可能にする。逆問題も恩恵を受け、勾配ベースのサンプリングによって高度に非線形なパラメータの推定がはるかに容易になる。さらに、装置設計においても、DPを活用することでより高度な最適化を達成できる。
本セミナーでは主に我々が開発している微分可能な系外惑星スペクトルのリトリーバル(大気物理化学量の推定) ExoJAXをもとに微分可能プログラミングをどのように天文学に応用したら楽しいか講演したい。
1829
2025/9/5 (Fri)
松井 理輝 (東北大学)
Prediction of multi-messenger emissions associated with X-ray flare of GRBs
Gamma-ray bursts (GRBs) are some of the most extreme transients in the universe, but their explosion and emission mechanism remains unclear. Their prompt emissions, which last around 10 seconds, are rarely observed at multi-wavelengths. This makes it difficult to extract information from these events. To overcome this problem, we focus on X-ray flares (XFs), which is X-ray emissions that occur 100 to 1000 seconds after the main burst. Since recently developed multi-messenger facilities can observe them, we calculated multi-messenger emissions associated with XFs. Considering the range of the dissipation radius and the Lorentz factor of the jet, we determine the parameter space in which a detectable flare can be produced at each messenger. We found that simultaneous ultraviolet, very-high-energy gamma-ray, and high-energy neutrinos associated with XFs can be detected by Swift/UVOT, SVOM/VT, CTAO, and IceCube-Gen2. The detection and non-detection rates for each detector are key to determining the uncertain yet essential values necessary for understanding the physics of GRB jets.
1830
2025/9/5 (Fri)
Lucy Olivia MCNEILL (Kyoto Univ.)
Binary stellar evolution of double white dwarf binaries: theoretical challenges revealed by ZTF
Interacting double white dwarf binaries are the progenitors of various astrophysical exotica, such as AM CVn binaries, type Ia supernovae, faint type Ib supernovae, hot B type subdwarf stars, and variable RCrB stars.
ZTF is detecting “short-period” binaries with periods less than 1 hour containing white dwarf stars. The growing sample includes both detached and mass transferring double white dwarf binaries within ~ 1 kpc. ZTF is also detecting their progenitor binaries which contain an evolved star and white dwarf. Importantly, the radii of binary components can be precisely measured in eclipsing searches.
The standard theoretical assumption has been that white dwarfs in short-period binaries are “cold” once they begin to interact via mass transfer. In that case, their stellar structure is described simply by degeneracy pressure.
Surprisingly, the eclipsing white dwarf binary sample reveals hot, bloated components which are only partially degenerate. This poses several problems with the current theoretical understanding of the binary stellar evolution which produces interacting double white dwarfs, and hence the diverse stellar populations and transients that follow.
Such understanding is also essential to detect and interpret the Milky Way population of double white dwarfs in data from future space-borne gravitational wave observatories. I will summarise new efforts model double white dwarf binary evolution. In particular, the inclusion of tidal heating as an additional energy source in the stars.
1831
2025/10/13 (Mon)
星 篤志 (東北大学)
Exploring the Relationship Between Low-Mass Supermassive Black Holes and Their Host Galaxies at Intermediate Redshift
Exploring low-mass black holes (BHs <10^8 Msun) across cosmic time provides a powerful means to study the origin of the BH-galaxy co-evolution. The James Webb Space Telescope (JWST) has recently uncovered a new population of faint active galactic nuclei (AGNs) hosting low-mass BHs that appear overmassive relative to their host galaxies at z>4, deviating from the local BH–galaxy scaling relations. To bridge the gap between such overmassive BH systems and those in the local universe, we investigate the properties of nine type-1 AGNs at intermediate redshift (2 < z < 4) selected from the JWST Advanced Deep Extragalactic Survey. All of them show the significant Hα broad line and the AGN contribution in the spectral energy distribution. Our sample covers BH masses of 10^{6.1-8.2} Msun and stellar masses of 10^{9.3-11.0} Msun, comparable to those of the AGNs observed in the local Universe. In the low-mass BH regime (<10^8 Msun), the BH-to-stellar mass ratios in our sample (0.01-0.1%) differ from those of the AGNs at z>4 (1-10%), suggesting that evolutionary pathways of BHs and galaxies may be different at intermediate and high redshift. We also perform 2D image decomposition using GALFIT to constrain the bulge mass by evaluating the bulge contribution in the rest-frame near-infrared flux. We identified the AGNs with low BH-to-bulge mass ratios compared to those observed in the nearby bulge-dominant galaxies. This suggests the presence of a galaxy-first evolutionary path, in which bulge formation occurs before substantial gas is efficiently accreted onto the central engine. Finally, I will also present initial results from the Subaru Prime Focus Spectrograph (PFS), obtained through systematic spectroscopic follow-up of X-ray sources to extend low-mass BH and AGN studies.
1831
2025/10/13 (Mon)
天崎賢至 (東北大学)
Cosmic very small dust grains as a natural laboratory of mesoscopic physics
Near and mid-infrared observations suggest the presence of nanoscale very small dust grains (VSGs).
These grains fall into the “mesoscopic” regime, where the finite grain size significantly influences their thermal and optical properties. For example, at low temperatures, energy level quantization limits the number of thermally accessible states, making it difficult to describe their thermal properties with bulk models. Such effects are not sufficiently incorporated in conventional dust models.
In this study, we construct a new emission model for carbonaceous VSGs by incorporating mesoscopic physics. We apply the method of energy level statistics to account for the contribution of free electrons to the low-temperature emission, and find that the spectral energy distribution of carbonaceous VSGs exhibits an excess emission at wavelengths beyond the far-infrared range.
I will also compare the model with observations, focusing on the submillimeter spectral slope, which varies among galaxies and is typically flatter than expected for ideal crystalline materials. I will discuss the possibility that our model may help explain this flattening.
1832
2025/10/20 (Mon)
千葉 凛平 (東京大学)
Probing dark matter with resonant dynamics of the Galactic bar
Galactic bars are elongated, rotating structures observed in more than two thirds of disk galaxies, including our own Milky Way. In the presence of dark matter in our Universe, these bars are predicted to gradually spin down by gravitationally transferring their energy and angular momentum to dark matter, a process known as dynamical friction. In contrast, modified gravity theories predict no bar slowdown, suggesting that the spin-down of galactic bars is a key indication of the existence of dark matter.In this talk, I will present the first implication for this deceleration of the galactic bar in the Milky Way from the kinematics and chemistry of stars trapped in resonance with the bar: just like tree rings, the resonantly trapped phase-space evolves inside-out, capturing new stars by expanding its surface as it sweeps towards larger angular momentum, while conserving the internal distribution. Using the recent data from the Gaia satellite, I will show that the bar's corotation resonance bears this tree-ring structure, allowing us to infer the bar's evolutionary history.
1833
2025/10/21 (Tue)
Gerhard Hensler (University of Vienna)
Extragalactic star formation in ram-pressure stripped gas clouds
Galaxies in clusters move through the hot intra-cluster medium (ICM)
mostly with virial velocities. By this, gas-rich galaxies are exposed to
the drag force of the ICM and suffer gas stripping. This well-known
ram-pressure stripping (RPS) process is observationally manifested and
appears in various facets. Not only the radial truncation of gas disks
with respect to the old stellar component and the gas evacuation of
dwarf galaxies, another fascinating process comes into the focus of
research: in such RPS gas clouds extragalactic stars can be formed.
From HI and optical surveys of the nearest galaxy clusters growing
numbers of isolated pure gas clouds as well as of isolated star clusters
get detected in the intra-cluster field. These RPSed star clusters can
provide insights into a bunch of widely studied and actually addressed
questions on the gas dynamics of RPS clouds, their survival and their
conditions of extragalactic star formation, on its timescale, on the
initial mass function at low star-formation rates, the decoupling of the
gas from star clusters to become naked, and the escape of their Lyman
continuum (LyC) radiation.
For these objectives we take advantage of the wealth of star clusters
around the Virgo cluster spiral galaxy NGC 4254. 60 young stellar
clusters are identified in the GALEX/FUV with different masses, ages,
and separations from the main gas disk. Half of them are still engulfed
by HII regions. This sample allows to derive age-dependent LyC escape
fractions and star-formation quenching times due to gas evacuation, both
depending on the mass of parent clouds. For more massive clouds the
assumption of a simple stellar population and the uncertainty of the
stellar mass sampling are investigated and will be discussed here.
1834
2025/10/27 (Mon)
Naoaki Yamamoto (Tohoku Univ.)
Young galaxy clusters/groups identified as overdensities of [OII] emission-line galaxies
We present a study of overdensities identified with [OII] emitters at z = 1.47 selected based on the narrow-band images taken with the Hyper Suprime-Cam on Subaru Telescope. We find 12 overdensities with statistical significance of >4σ within totally 2.8 deg2 area in COSMOS and SXDS-XMMLSS fields. Most of these overdensity regions are dominated by star-forming galaxies (emission-line galaxies), unlike local clusters dominated by red quiescent galaxies. These are the new class of galaxy clusters/groups still in a young evolutionary stage which would have been missed by previous conventional cluster finders such as those to search for red-sequence galaxies. Star-forming galaxies in these overdensity regions show no clear differences from those in the general field in stellar mass, star formation rate (SFR), specific SFR (sSFR), or ΔMS, deviation from the star-forming main sequence. We attribute this lack of dependence to the short timescale of quenching from the main sequence to the quiescent regime, and/or detection limit of narrow-band selection, and/or earlier evolutionary phases of galaxy clusters/groups discovered in this work. We also find that the emission-line galaxies with red colors, which are among dusty star-forming galaxies, AGNs and quenching galaxies, tend to reside in overdensity regions, suggesting that these galaxies are under the influence of environmental effects. Finally, the giant-to-dwarf ratio for the red-sequence galaxies does not show any significant environmental dependence, probably due to low statistics. But it may mean that low-mass galaxies are yet predominantly forming new stars actively and have not grown to quiescent galaxies irrespective of environment. Overall, our overdensities selected with [OII] emitters are still at early evolutionary stages of cluster/group growth with higher star formation activities, and environmental effects are not yet the primary driver of galaxy quenching.
1834
2025/10/27 (Mon)
金 滉基 (東北大学)
2次元一般相対論的Particle-in-Cellシミュレーションによる磁気圏由来
フレア発生過程の解析
活動銀河核では、しばしばガンマ線帯での増光現象(フレア) がみられる。その起源
は未解明であるが、ブラックホール(BH) 半径/光速以下の短時間変動を示すことから、
近年ではBH 最近傍の強磁場領域(磁気圏) での粒子加速過程に注目が集まっている。
数年内のCTAO 全面稼働により観測例が増加し、フレア発生過程の検証が進む期待が
あることを踏まえ、発生領域・機構が異なるこれらの過程について、粒子加速効率、
ガンマ線放射特性を定量的に比較することが重要である。
そこで本研究では、2次元一般相対論的プラズマ粒子シミュレーションを用いて、BH
磁気圏での粒子加速過程の解析を行った。その結果、 BH 回転軸方向に磁力線に沿っ
た方向の強電場が準周期的に発生する一方、赤道面付近で自発的に磁気リコネクショ
ンが発生する様子が見られた。こうした変位電流の発生や磁気リコネクションに伴う
プラズモイドの落下は、磁気圏中の大局的ポロイダル電流構造の維持に深く関与する。
講演では、こうした磁気圏内部の活動が活動銀河核ガンマ線帯フレアの起源となる可
能性について議論する。
1835
2025/11/10 (Mon)
Yoshihisa Suzuki (Tohoku Univ.)
Unveiling the formation of the Milky Way halo using Subaru Hyper-Suprime Cam
In the ΛCDM framework, galaxies are thought to have been formed and evolved through the successive accretion of dark-matter subhalos. The fossil records of these events are imprinted in the stellar halo as spatially coherent overdensities and substructures, making the study of the stellar halo a key to understanding the assembly history of the Milky Way (MW). In this work, we investigate the spatial density profile of the MW stellar halo using deep and wide-field photometric data obtained with the Subaru Hyper Suprime-Cam. By selecting abundant main-sequence turnoff stars as halo tracers and carefully modeling both statistical and systematic uncertainties, we have derived a robust halo density profile. Our analysis has revealed that the stellar halo follows a double power-law model, with a clear transition around 20 kpc from the Galactic center. Beyond this radius, the halo is dominated by significant substructures. By comparing these substructures with dynamical simulations following the orbital motion of the Large Magellanic Cloud (LMC), we find indications that the LMC is now in the second passage phase - the previous pericenter passage occurred around 7 Gyr ago, left the tidal debris, and this may correspond to the diffuse substructure that we have identified toward Bootes. These results suggest that the LMC has exerted a long-term dynamical influence on the formation and present-day structure of the MW halo.
1835
2025/11/10 (Mon)
Rin Oikawa (Tohoku Univ.)
Mass loading into black hole jets in Active Galactic Nuclei
Black hole jets are a highly collimated plasma outflow ejected from the vicinity of a black hole
and accelerated to nearly the speed of light. They have been observed from the supermassive black
holes at the centers of galaxies, including M87, where the black hole shadow has been directly
imaged. The Blandford–Znajek process, which extracts rotational energy from a black hole via
magnetic fields, is widely believed as the fundamental mechanism powering such jets. However, the
plasma loading mechanism into the jets remains unresolved.
In this study, we calculate the pair production rate of electrons and positrons generated by gamma
rays from non-axisymmetric magnetic reconnection regions near the black hole, employing general
relativistic ray tracing to derive their spatial distribution. The results naturally reproduce the
plasma densities inferred from observations of M87 and are consistent with the non-detection of a
jet in SgrA*. In the presentation, we discuss how the obtained spatial distribution relates to the
limb-brightening structure and possible acceleration mechanisms of jets, and we also address the
prospects for testing this model through future multi-wavelength simultaneous observations.
1836
2025/11/11 (Tue)
Sebastiano Cantalupo (Univ. of Milan)
Illuminating the most massive Cosmic Web nodes and their relation with galaxies at z~3 with the help of quasars
Our standard cosmological model predicts that most of the matter in the universe is distributed into a network of filaments - the Cosmic Web - in which galaxies form and evolve. Because most of this material is too diffuse to form stars, its direct detection in emission has remained elusive for several decades leaving fundamental questions still open, including: How are galaxies linked to each other? What are the morphological, physical and kinematical properties of the Cosmic Web on both large and small scales? How do they affect galaxy and AGN formation and evolution? During the last few years, we have been able to address these questions in a completely new way: i.e., by directly detecting intergalactic gas in emission thanks to “cosmic flashlights” such as quasars which can light-up through fluorescent emission cosmic gas over large volumes. Recent surveys with MUSE and KCWI are now providing a large statistical sample of three-dimensional images of rest-frame-UV line emission from “cold” gas haloes (and sometimes filaments) around galaxies, which are ubiquitously detected in the surrounding of quasars at all explored redshifts (2 < z < 6.5). In this talk, I will review these exciting results and discuss how they can provide new learning opportunities for our understanding of the physical properties of gas around massive galaxies and high-redshift galaxy formation. In particular, I will present recent deep and wide follow-up studies using ALMA, JWST, Chandra and HST on some quasar fields which are revealing the Cosmic Web distribution on Mpc-scales associated with the largest galaxy and AGN overdensities found so far at high redshift. These surveys are providing surprising results on the properties of galaxies and AGN within rich environments and give us the unique opportunity to directly correlate galaxy and intergalactic gas properties as measured in emission.
1837
2025/11/17 (Mon)
熊田遼太 (東北大学)
ストリーミング不安定性でつくられるダスト塊のスケーリング則と微惑星形成条件
1型X線バーストは, 中性子星と低質量星からなる連星において生じる突発天体現象である.
その起源は中性子星表面での暴走的な核燃焼であり,
元素合成の過程でp核とよばれる同位体の一部を合成しうる.
もし核燃焼の生成物が中性子星から放出されるならば,
1型X線バーストは, 太陽系における軽いp核の起源の候補のひとつとなりうる.
しかし, これまで1型X線バーストでどれくらいの質量がどれくらい放出されるのかは定量的に求められてこなかった.
他方, 近年になり1型X線バーストの数分後に電波でのフレアが報告された.
本研究では, この電波放射を遷相対論的な速度で伝播する衝撃波と周辺ガスとの相互作用による
電子シンクロトロン放射に由来すると仮定し,観測の光度曲線を再現するような質量放出量とその速度を推定した.
その結果, 光度曲線のピークを再現するには, 10^-15太陽質量程度の質量を,
光速の10%程度の速さで放出している必要があることが分かった.
この放出質量は, 降着質量の0.1%に相当する.
本発表では, この放出質量が太陽組成を仮定した銀河系の軽いp核の量を
説明するのに十分かどうかまで議論する.
1837
2025/11/17 (Mon)
鈴木慧次 (東北大学)
巨大惑星と原始太陽系円盤の1次元共進化計算による惑星形成環境の解明
巨大惑星形成は形成環境である原始太陽系円盤にも大きな影響を与え、それがまた巨大惑星形成にフィードバックされる。
特に複数巨大惑星の形成では、このフィードバックを含めた共進化が重要となる。
本研究では、この複数巨大惑星と原始太陽系円盤の共進化を光蒸発に円盤消失機構を加えた1次元モデルのシミュレーションで調べる。
惑星円盤共進化は多次元流体計算によりすでに研究されてきたが短期間計算に限定されており、通常数百万年で進行する惑星円盤共進化を解明することはできていない。
本研究では、太陽系での木星・土星形成と系外巨大惑星系形成について調べた。
木星と土星は、従来、最小質量円盤モデル(または林モデル)内での形成が想定されてきた。
しかし、本研究の結果、最小質量円盤内で木星と土星がガス降着で重くなりすぎることがわかり、その
1/10以下の質量の円盤が適していることが示された。
これは両惑星へのガス降着開始時に円盤は消失しつつある状態にあったことを示している。
さらに、本モデルを系外惑星系のPDS 70の系にも適用した。
PDS 70の系では2つの巨大惑星が円盤内で形成途中にあることが観測されており、惑星、円盤の質量の他に惑星への降着率等も測定されている。
本研究ではこれら各観測データを同時におおよそ再現するモデル作成に成功した。
またこの系を模擬した従来の短期間流体計算もよい精度で再現できることも確認した。
1837
2025/11/17 (Mon)
和田航汰 (東北大学)
ストリーミング不安定性でつくられるダスト塊のスケーリング則と微惑星形成条件
微惑星形成過程は惑星形成理論の最大の難問題である。現在は原始惑星系円盤のダスト層
のストリーミング不安定性でつくられる高密度ダスト塊から微惑星が形成されたとする説
が最有力となっている。従来のストリーミング不安定性の数値シミュレーションでは、主
にシミュレーション内の最大ダスト密度に着目し、これが重力不安定を生じさせるロッシェ
密度を超えるか否かで微惑星形成条件が議論されてきた。本研究では、ダスト塊の密度分
布やサイズなどの統計的性質を明らかにすることで、微惑星形成条件等をより正確に議論
することを目的とする。我々は、従来と同様にダスト平均密度、ダストサイズ、サイズ分
布の有無を変え、ストリーミング不安定性の2次元軸対称数値シミュレーションを多数実
行した。ダスト塊のサイズの情報を得るため、計算データからダスト2体相関関数を求め
た。その結果、ダスト塊のサイズは、ダストとガスの相対ドリフト速度に比例し決まって
いることが分かった。ストリーミング不安定性のエネルギー源はダストの動径方向のドリ
フト運動であるため、この結果は妥当である。ダスト密度の確率分布は対数正規分布であ
ると分かった。この密度分布は、密度を平均密度で規格化すると他のパラメータにはほと
んど依らず、ダストサイズに弱く依存するのみであった。さらに、ダスト密度分布を用い
て微惑星形成条件を求めた。得られた条件は従来研究と類似しているが、より小さなダス
トサイズで微惑星が形成されやすいことが示された。さらに、塊内でのダスト衝突速度や
ダスト成長率に対しても調査し経験式を得た。
1838
2025/11/26 (Wed)
田邊ひより (東北大学)
すばる望遠鏡レーザートモグラフィー補償光学のトモグラフィー波面推定の最適化
レーザートモグラフィー補償光学(LTAO)はコーン効果を減少させるために複数のレーザ ーガイド星を用いて測定を行い、高さ方向に分解した推定を行うことで、ターゲットに最適 化した補償を実現することができる。ULTIMATE-START プロジェクトは、すばる望遠鏡 に LTAO を実装し、可視光において回折限界を実現することを目的として波面センサーを 含めた開発を進めている。本研究では現在開発中の LTAO 波面センサーの光学実験で得ら れたデータを解析することで、実際の観測で想定される残留波面誤差を推定し定量的に評 価することを目標としている。解析では 2025 年に国立天文台ハワイ観測所実験室で LTAO 波面センサーに搭載されている 4 つの波面センサーと Truth-WFS unit に搭載されている 1 つの波面センサーにシミュレーション光源からの光を入れて大気揺らぎを測定したデー タを使用している。位相板を用いて 4 つの LTAO 波面センサーの情報から波面の再構成を 行い、Truth-WFS の波面を再構成した結果との比較を行なう。この際、観測に即した波面 推定を実現するために、LGS の配置などで幾何学的に定まる幾何学的配置での波面再構成、 再構成した波面の模様が一致する相関配置での波面再構成、補償光学における補正手法の 一つである Learn&Apply 法を応用して求めた配置での波面再構成の 3 種類の手法を比較し、 残留波面誤差が最も小さくなる手法の同定ならびに測定に即した配置を求める。この解析 により Truth-WFS と同様の波面揺らぎパターンが LTAO 波面センサーで推定された。 また、幾何学的配置、相関配置、Learn&Apply 法での配置を用いた時の残留波面誤差はそ れぞれ 0.521 μm, 0.619 μm, 1.92 μm であった。観測データのみを用いて再構成を行っ た時の残留波面誤差は 0.098um であるため、適切な補正を行うためには観測を反映したモ デル配置を求め、それに基づいてキャリブレーションを行う必要があり、その手法について 議論を行う。
1838
2025/11/26 (Wed)
Koya Chiba (Tohoku Univ)
Non-LTE Ionization Modeling in Neutron Star Merger Ejecta
The material ejected from a binary neutron star merger is thought to produce a radioactively powered emission, known as a “kilonova”, observable in the ultraviolet, optical, and infrared wavelengths. In 2017, following the detection of gravitational waves from GW170817, the associated kilonova AT2017gfo was observed.
Recent studies have identified absorption and emission features in the spectra of AT2017gfo; however, the estimated elemental abundances in GW170817 still carry large uncertainties due to the simplified treatment of ionization in existing models. In particular, most previous studies have assumed local thermodynamic equilibrium (LTE) for the early-phase spectra.
This assumption may not be valid, since the ionization states of the ejecta can be affected by high-energy electrons produced by radioactive decay. In this study, we construct non-LTE ionization models for the early-phase spectra to better estimate the elemental abundances in GW170817.
By modeling the absorption feature around 1 μm, we constrain the abundances of helium (He) and strontium (Sr), which are candidate elements contributing to this feature. We find that approximately 0.01 – 0.1% Msun of He or Sr is present in the ejecta. In this presentation, we discuss the implications of these results for nucleosynthesis and mass ejection mechanisms in neutron star mergers.
1838
2025/11/26 (Wed)
Salma Rahmouni (Tohoku Univ)
Heavy Element Features in Early- and Late-Phase Spectra of Kilonovae
Binary neutron star mergers are considered a promising site for heavy element nucleosynthesis via the rapid neutron capture process (r-process). Their electromagnetic emission, known as “kilonova”, is powered by the radioactive decay of the freshly synthesized nuclei.
Following the detection of gravitational waves (GW170817) from a neutron star merger in 2017, the observed electromagnetic counterpart (AT2017gfo) provided direct evidence of the occurrence of r-process in neutron star mergers. However, identifying individual elements responsible of the spectral features of this event remains challenging.
In this work, we systematically searched for all infrared transitions of heavy elements using experimentally calibrated energy levels to identify candidates for individual features. By including both allowed (E1) and forbidden (M1) transitions, we conducted a comprehensive analysis on both early and late-time spectra of AT2017gfo.
Our radiative transfer simulations of the early-phase spectra suggest Gd III as a new candidate for an observed absorption feature. On the other hand, our constructed spectral model for the late-phase spectra indicates that La III, Ce III, and Te III likely dominate three late-time emission features. We finally argue that these identifications suggest that the abundance pattern synthesized in GW170817 is consistent with the solar r-process pattern.
1839
2025/12/1 (Mon)
鍋田春樹 (東北大学)
非理想磁気流体効果を考慮した磁気乱流環境下でのダスト濃集
標準的な惑星形成の過程ではμmサイズの固体微粒子(ダスト)が集積し、惑星の種であるkmサイズの小天体(微惑星)が作られる。微惑星の形成過程としてこれまではダストが落下する前に中心面へ沈殿したダストの層が濃集し、重力不安定で微惑星が作られるというシナリオが提案されていたが、ダストの沈殿は原始惑星系円盤内の乱流により妨げられ、重力不安定を引き起こすには不十分だと指摘されている。
乱流の起源のひとつは、原始惑星系円盤内の磁場によって駆動される磁気回転不安定性であると考えられており、磁場は乱流構造を作りダストの濃集を妨げる一因とされてきた。原始惑星系円盤では電離度が低くガスと磁場の結びつきが弱くなり磁場がガスから拡散する領域が存在するため、微惑星形成はそのような磁気乱流が不活性となる領域で起こると考えられてきた。しかし近年の研究(e.g. Xu & Bai, 2022)は、ダストの運動と磁場を同時に解いた数値計算により、磁場により生じた乱流的な環境下でもダストの濃集が可能であることを示唆している。
以上を受けて本研究ではダストを含む非理想磁気流体の局所シアリングボックス計算により、磁場の拡散とダストのサイズをパラメータとして、磁気乱流環境下でのダストの濃集が可能となる原始惑星系円盤の領域の条件を調べた。その結果、磁場の拡散が強くダストのサイズが大きい場合にダストの濃集が実現することが分かった。先行研究(Marchand, et al., 2020)の磁気拡散を考慮した大局的な円盤形成のシミュレーションと比較して、本研究の結果における濃集可能な磁気拡散の強さは円盤の30au以内の内側、ダストサイズは1cm以上に対応すると考えられる。本発表ではパラメータによるダスト濃集のふるまいの違いと、考えられる濃集メカニズムについて議論する。
1839
2025/12/1 (Mon)
越水 拓海 (東北大学)
磁束輸送を考慮した孤立ブラックホール降着流の多波長放射モデル
銀河系内には、単独で浮遊する恒星質量ブラックホール(Isolated Black Hole; IBH)が多数存在すると理論的に予想されている。IBHは連星相互作用の影響を受けず、大質量星の終末進化を純粋に反映する天体であり、単独星の進化や降着流の物理を検証する上で重要な対象である。しかし、観測例はSahu et al. (2022) による重力マイクロレンズ事象の1例にとどまっている。本研究では、降着円盤からの放射を手がかりとしてIBHの検出可能性を検討する。
近年、IBHが分子雲ガスを降着して強く磁化した降着円盤(Magnetically Arrested Disk; MAD)を形成し、磁気リコネクション加速によって可視光〜X線放射を生じる可能性が指摘されている(Kimura et al. 2021)。しかし、従来モデルは磁束保存を仮定しており、放射強度を過大評価している可能性がある。また、可視光・軟X線は分子雲のガス・ダストの減光の影響を受けて、観測に大きな制限が付く。
本研究では、磁束の輸送を考慮した一次元の放射モデルを構築した。このモデルの拡張により、分子雲の減光の影響を受けにくい赤外線帯域において、放射強度が相対的に増大することを示した。また、分子雲の数密度やIBHの分子雲に対する相対速度をパラメータとして磁束輸送を計算し、多くの場合にMADが形成されることが分かった。MADが形成される場合、他の候補天体(白色矮星連星や原始星など)よりもX線で明るく観測される可能性がある
1839
2025/12/1 (Mon)
米永直生 (東北大学)
偏光輸送計算で迫るガンマ線バーストの放射メカニズム
ガンマ線バースト(GRB) は、大質量星の重力崩壊や連星中性子星合体に由来すると考えられる爆発現象で、その数秒から数千秒間続く即時放射は電磁波として宇宙で最も明るい放射を放つ。GRB の放射機構は未解明であり、従来のスペクトル解析では光球放射かシンクロトロン放射かを区別することは困難である。そこでスペクトルとは独立な情報である偏光を組み合わせることで放射機構を解明できることが期待されている。次世代のGRB 偏光検出器であるPOLAR-2 は、30–800 keV 帯でGRB の偏光測定が可能であり、2027 年の運用開始が予定されている。光球放射モデルでは、複数のGRB イベントにおいて10–100 keV 帯で偏光度(PD)が20–30%ほどに達し得ることが示されている(Lundman et al. 2018)。本研究では、これまで考慮されていなかった熱的電子によるファラデー回転に起因する消偏光を偏光輸送計算に導入し、観測されるPDのエネルギー依存性を求めた。その結果、GRB 090902Bに対して従来予測と比べPDは30 keV以下で抑制され、数十 keV付近に立ち上がりが現れることを示した。このPDのピークエネルギーは電子密度や磁場強度に依存し、これらは観測によって推定できる。本講演では、ファラデー効果による消偏光過程を考察し、GRB放射機構(光球放射/シンクロトロン)の識別と電子密度・磁場強度などを含むモデルパラメータの制限に加え、POLAR-2による検出可能性についても議論する。
1840
2025/12/8 (Mon)
Mitsuaki Takahashi (Tohoku Univ.)
Development of ISP for Adaptive Optics using FPGA
In terms of optics, Adaptive Optics (AO) is an optical system operating as auxiliary observational instrument to achieve a diffraction-limited PSF (Point Spread Function) on large ground-based optical-infrared telescopes, such as the 8.2-meter Subaru Telescope. But at the same time, in terms of engineering, AO is an application-specific computer system that requires real-time performance to directly handle natural phenomena. Specifically, AO performs wavefront measurement with a wavefront sensor, control computation with digital ICs (Integrated Circuits), and wavefront correction with a deformable mirror, all within 1 ms and continuously, enabling the telescope to keep the light sharply focused on the science instruments. However, because the control computational complexity is proportional to the fourth power of the telescope aperture, there is a challenge in that performing wavefront correction within 1 ms becomes difficult for 30-40 m class telescopes, such as TMT (Thirty Meter Telescope). Therefore, in my research, I am developing a semiconductor chip optimized for AO by using an FPGA (Field Programmable Gate Array), a reconfigurable digital IC that allows custom logic design even at the laboratory scale. Specifically, my research aims to develop an ISP (Image Signal Processor) for a wavefront sensor and to shorten the processing time in AO by performing image processing with low latency through hardware processing implemented in dedicated digital circuits. In this presentation, from a computer engineering perspective, I will discuss what kinds of architectures and algorithms I am implementing to shorten the processing time in AO.
1840
2025/12/8 (Mon)
Miku Funaki (Tohoku Univ.)
Probing cold gas associated to protocluster and surrounding structures
The cold gas accretion to proto-clusters and to galaxies therein is expected to be very efficient at z>2 by the cold stream mode. As the proto-clusters grow in mass, the gas is shock-heated to a high temperature, leading to the full ionization of the ICM eventually. This transition in the gas phase is probably responsible for the rise and fall of star forming activities in proto-clusters. In order to observationally test this working hypothesis, we need to map cold gas distribution along large scale structures, in which proto-clusters are developed at intersections of filaments.
We employ a unique method of panoramic pair narrow-band (NB) imaging focusing on the difference in attenuation between Hα and Lyα lines due to resonant scattering and dust extinction.
We conducted a NB imaging with HSC/Subaru across 1.5-degree scale structures at z=2.23 hosting a known rich proto-cluster in the COSMOS field. We have identified over 200 Ly-alpha emitters (LAEs) over a 140 cMpc x 140 cMpc region. By comparing with H-alpha emitters (HAEs) traced by HiZELS NB imaging across the same field, we mapped out the HI gas along the filaments and in the group/core based on differential spatial distributions of the two populations and their radial light profiles of the lines. As a result, we discovered a cold gas association neatly tracing the structures. We will discuss how the cold gas is accreted to proto-cluster and how it regulates star formation in galaxies.
1840
2025/12/8 (Mon)
浜田草太郎 (東北大学)
連星白色矮星合体残骸候補J005311の細長いフィラメント構造について
1181年の歴史的超新星爆発 (SN 1181) の残骸候補とされているJ005311 は連星白色矮星の合体によって生まれたと示唆され、中心の白色矮星からの高速風と、極めて特異な放射状のフィラメント構造を持つことが近年の観測により明らかになっている 。特に、等方的に伸びる細い「指状」のフィラメント構造は他の超新星残骸には見られない特徴であり 、その形成メカニズムの解明は白色矮星合体に付随する質量放出のダイナミクスを理解する上で重要である 。 本研究では、このフィラメント構造の起源として、エジェクタと星間物質 (ISM) の相互作用における流体力学的不安定性に着目した。具体的には、衝撃波面での放射冷却が効くことでシェルが薄くなり、そこにVishniac不安定性が成長することで面密度に疎密が生じ、密度の薄い領域から背後のエジェクタが突き抜けることでフィラメントが形成されるというシナリオを検証する。エジェクタとISMとの衝突による衝撃波をモデル化し解析的に解くことで、vishniac不安定性が発現するかの評価を行った 。その結果、衝撃波形成後のある段階において、Vishniac不安定性の発現条件を満たしうることが示唆された 。さらに、この環境下での摂動の成長と非線形進化を調べるため、数値流体シミュレーションを行った。本発表では、観測されているJ005311のフィラメント構造が、冷却によって誘起される流体力学的不安定性によって説明可能か議論する。
1841
2025/12/15 (Mon)
Misato Fukagawa (Tohoku Univ.)
Unveiling the Structures of Protoplanetary Disks with High-Resolution Observations
Protoplanetary disks are the sites of planet formation, and recent advances in observations achieving spatial resolutions of ~10 au or better with sufficient sensitivity have substantially improved our understanding of their structure and dynamical evolution. This talk reviews results from near-infrared imaging of young stellar objects using Subaru, with particular emphasis on morphological features such as spiral arms, rings, gaps, and asymmetric structures. In addition, ALMA observations of continuum emission and molecular lines place constraints on the spatial distribution of solids, grain growth, and gas kinematics in disks, and in a few cases reveal signatures consistent with the presence of embedded protoplanets. Observations of systems hosting large (>100 au) disks further suggest that physical processes such as gravitational instability and disk–planet interactions play important roles in shaping disks from early evolutionary stages. Taken together, infrared and submillimeter observations provide a view in which dust evolution and gas dynamics jointly regulate disk architectures.
1842
2025/12/15 (Mon)
Jun Toshikawa (Tohoku Univ.)
The formation of galaxy clusters probed by the Subaru/HSC imaging and Ly-alpha spectroscopy
Galaxy clusters play a key role in both the formation of cosmic structures and environmental effects on galaxy formation/evolution. We have searched for the progenitors of galaxy clusters, “protoclusters”, at high redshifts in order to reveal the early phase of cluster formation. Thanks to the wide-field imaging capability of the Subaru/HSC, a large number of protocluster candidates were identified at z>3. This systematic sample of protocluster candidates enables us to investigate 1) the halo mass of protoclusters by their clustering strength, 2) the correlation between protoclusters and peculiar galaxy populations (e.g., QSOs and radio galaxies), 3) star-formation activity in high-density environments.
Following these studies with the imaging dataset, we have been carrying out follow-up spectroscopy targeting Ly-alpha emissions and characterizing protoclusters in terms of their three-dimensional structures and Ly-alpha properties. Although we have discovered several protoclusters by the same dataset and method, each protocluster exhibits unique features on the 3D distribution and/or physical properties of member galaxies. The diversity of protoclusters may reflect the difference of developmental stages. In this talk, I will overview our protocluster project in the HSC survey and show the latest results mainly based on Ly-alpha spectroscopy.
1843
2026/1/7 (Wed)
Kohta Murase (Pennsylvania State Univ.)
Multimessenger Perspectives on High-Energy Cosmic Neutrinos
The discovery of high-energy cosmic neutrinos has opened a new frontier in astroparticle physics, providing a unique window into the most extreme environments in the universe. Identifying their sources is not only key to understanding neutrino origins, but also central to solving the century-old mystery of cosmic-ray origins and their acceleration mechanisms. In this talk, I will discuss the theoretical implications of the latest observations and highlight the growing impact of multimessenger approaches in this field. I will present recent developments on high-energy neutrino emission from extragalactic gamma-ray–dark sources and from regions near the Galactic plane. If time permits, I will also explore the potential of high-energy neutrinos as probes of physics beyond the Standard Model.
1845
2026/1/26 (Mon)
Fumihiro Naokawa (Univ. of Tokyo)
Cosmic birefringence
Several recent studies analyzing the polarization of the Cosmic Microwave Background (CMB) has reported 'cosmic birefringence'. This effect refers to a rotation of polarization plane of photons during their propagation (e.g. Komatsu 2022). Since this phenomenon violates parity symmetry, the signal, if confirmed, could provide a powerful probe of new physics such as Axion-like particle, dark matter and dark energy (e.g. Fujita et al. 2021). In this talk, I review the current observational status of cosmic birefringence and discuss the associated challenges. I also introduce independent and complementary measurements using astrophysical sources, such as radio galaxies (e.g. Carroll et al. 1990, Naokawa 2026).
1846
2026/2/17 (Mon)
高橋慶太郎 (熊本大学)
SETIを次の段階へ
SETI(Searching for Extra Terrestrial Intelligence)は系外惑星からの人工的な電波放射を検出し、地球外文明の存在を探索する研究である。SETIはこれまで様々な電波望遠鏡を利用して行われてきたが、2030年頃に観測を開始する次世代電波望遠鏡SKAは、その高感度・広帯域・多ビーム観測により探索空間を桁違いに広げてSETI研究を加速すると期待される。本講演では、惑星上に広く分布し狭い帯域を持つ電波源からの集団的なシグナルのスペクトルとその時間変動から、イメージでは点状にしか見えない惑星上の電波源空間分布を推定する方法を提案する。これは惑星の自転によるドップラー効果を利用するもので、ドップラー効果の大きさが惑星の自転軸の向きや電波源の緯度に依存することがキーとなる。デモンストレーションとして地球を地球外文明としてモデル化し、電波源分布を人口分布に比例させて集合的なスペクトルとその時間変動をシミュレーションする。そして時間変動パターンから逆解析して電波源分布の球面調和展開係数を求め、電波源分布を復元する。この方法はSETIを単なる人工電波の検出から、文明やその背後にある大陸・気象などの分布を探索する方法へとアップグレードするものである。最後におまけとして、知的生命が生まれた惑星に科学技術を基盤とする文明が発達するための、惑星系的条件について考察する。
1847
2026/2/27 (Mon)
Yuki Isobe (Univ. of Cambridge)
Tracing Early Chemical Enrichment in the Era of Ever-Growing JWST Data
Chemical abundance ratios trace the contributions of stars of different masses to the chemical enrichment of galaxies. For example, the nitrogen-to-oxygen (N/O) ratio is generally expected to increase with galaxy age: massive stars initially eject alpha-elements through core-collapse supernovae, while delayed contributions from lower-mass stars enhance the nitrogen abundance. This standard evolutionary picture has been challenged by the recent discovery of nitrogen-to-oxygen enhanced galaxies (NOEGs) at high redshift with JWST/NIRSpec. Intriguingly, a fraction of them exhibit signatures of active galactic nuclei (AGN). In this talk, I will review these chemical abundance anomalies, with particular emphasis on the connection between nitrogen enhancement, dense gas, and AGN activity. I will also discuss related anomalies, alpha-element enhancement, and dust depletion in the general population of high-redshift star-forming galaxies, which can now be robustly explored using hundreds of deep NIRSpec spectra combined with spectral stacking techniques.
過去の談話会
FY2024 (#1760-#1810)
FY2023 (#1718-#1759)
FY2022 (#1676-#1717)
FY2021 (#1645-#1675)
FY2020 (#1614-#1644)
FY2019 (#1570-#1613)
FY2018 (#1528-#1569)
FY2017 (#1487-#1527)
FY2016 (#1447-#1486)
FY2015 (#1406-#1446)
FY2014 (#1380-#1405)
FY2013 (#1355-#1379)
FY2012 (#1328-#1354)
FY2011 (#1302-#1327)
FY2010 (#1282-#1301)
FY2009 (#1249-#1281)
FY2008 (#1225-#1248)
FY2007 (#1191-#1224)
FY2006 (#1155-#1190)
FY2005 (#1124-#1154)
FY2004 (#1095-#1123)
FY2003 (#1057-#1094)
FY2002 (#1023-#1056)
FY2001 (#985-#1022)
FY2000 (#956-#984)
FY1999 (#925-#955)
FY1998 (#895-#924)
FY1997 (#858-#893)
FY1996 (#827-#852)